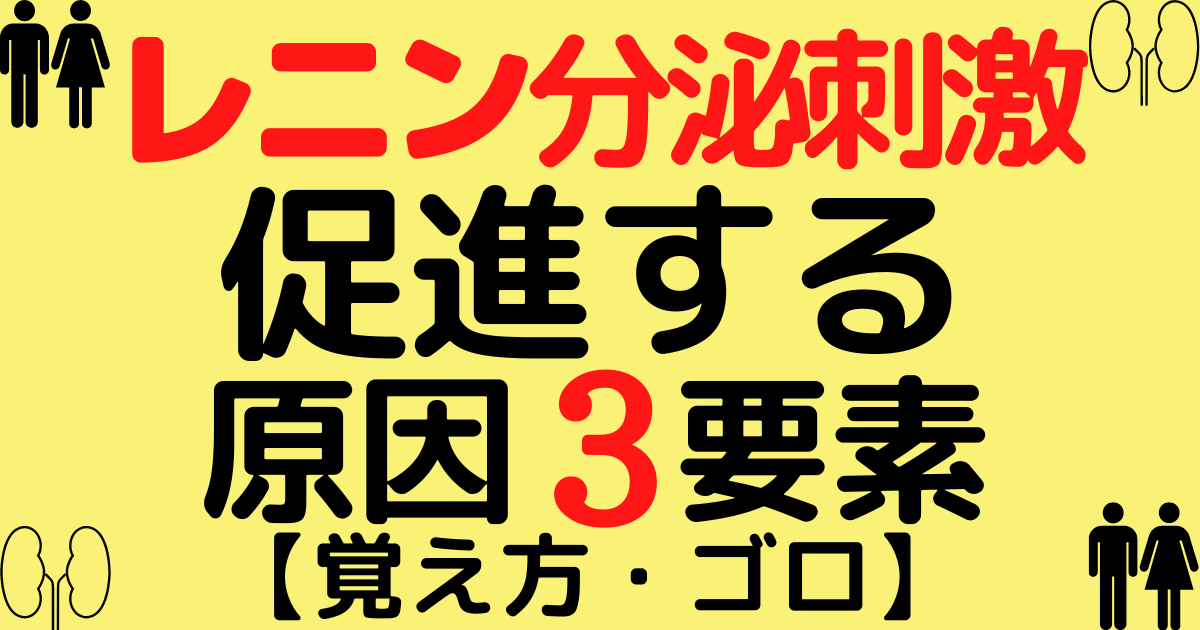悩む人
悩む人レニン分泌刺激ってどう覚えたらいいの~???
こういった悩みを解決します。
本記事では 「レニン分泌を促す3要素」の覚え方・ゴロ に加えて、
試験にでるポイント(傍糸球体装置)について解説します。
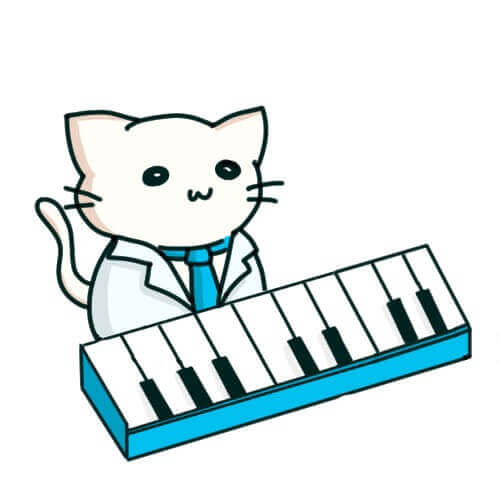
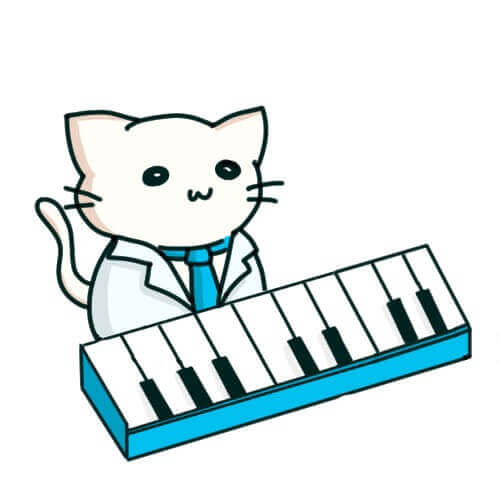
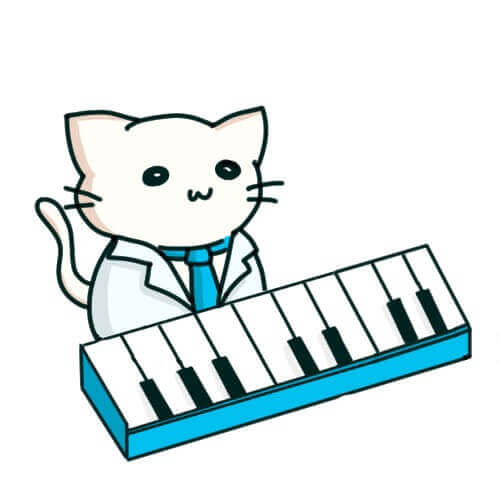
病態生理でレニンの理解は大切だよね!
最後にレニン・アンジオテンシン・アルドステロン系の記事をまとめたので、
不安な人は見てみてください(^^♪
【原因】レニン分泌刺激の3要素と傍糸球体装置の覚え方・ゴロ【CBT国試対策】
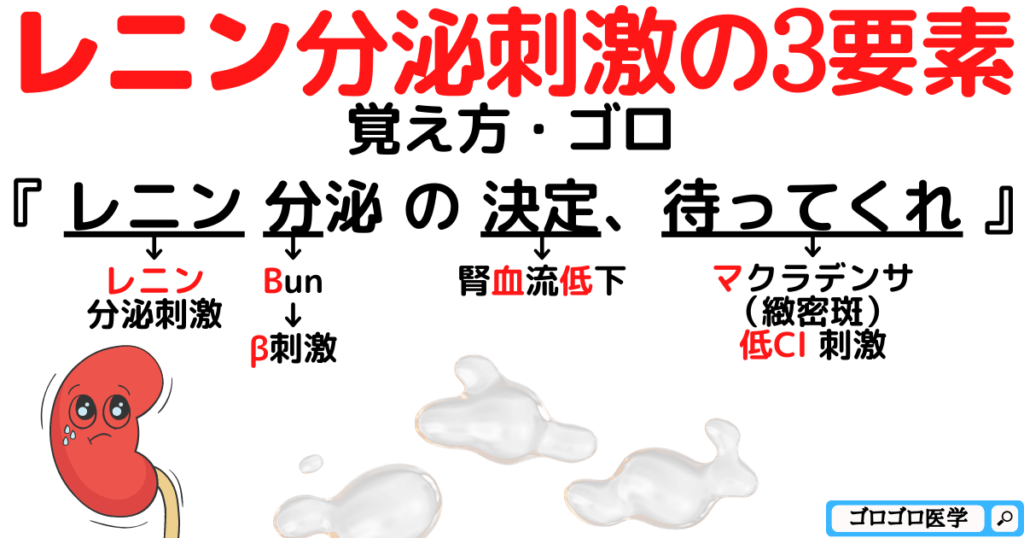
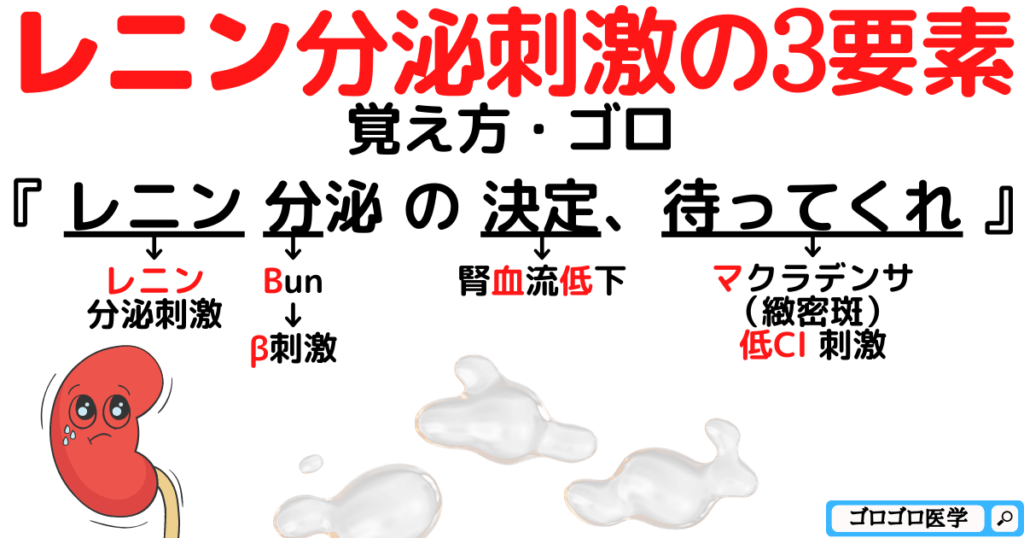
ゴロ:レニン分泌の決定、待ってくれ
レニン→レニン
分泌の→Bun→β刺激
決定→腎血流低下
待ってくれ→マクラデンサ(緻密斑)への低Cl 刺激
レニン分泌は以下の3要素で決まります。
- β刺激
- 腎血流の低下
- マクラデンサ(緻密斑)への低Cl刺激
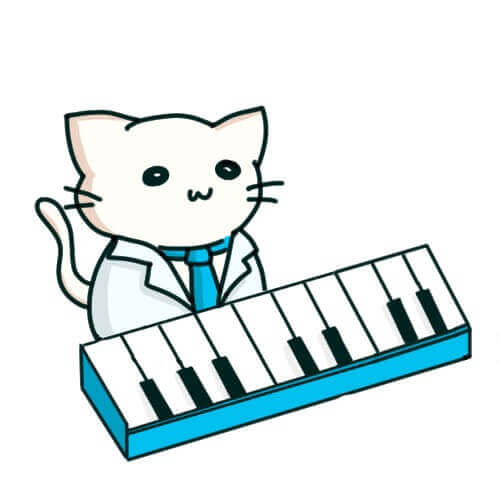
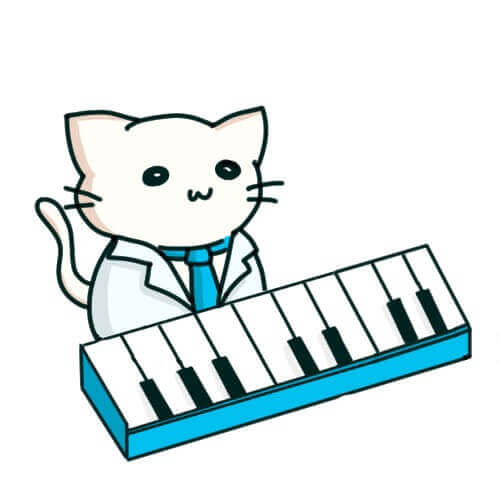
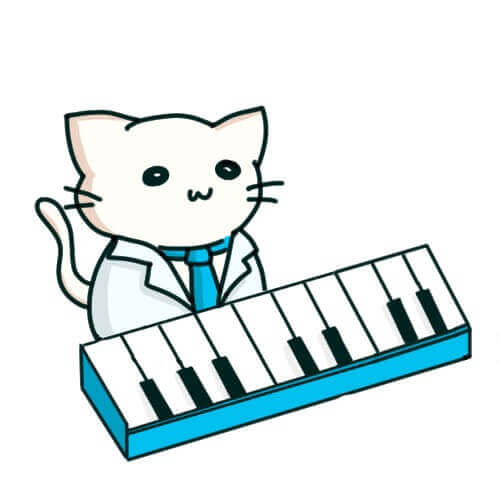
レニン分泌の意味を考えると、ゴロを覚えるまでもないですよ~(>_<)。
レニンは昇圧に関与します。
つまり、①血圧が低下した時に、②血圧を上げようと レニン分泌が亢進します。
①血圧が低下した時 →腎血流低下、低Cl刺激 が生じる
②血圧を上げよう →β刺激 が生じる
したがって、腎血流低下、低Cl刺激、β刺激がレニン分泌を亢進させます。
傍糸球体装置JGA: juxtaglomerular apparatusとは


※画像上は密集斑になっていますが、国家試験的には「緻密斑(マクラデンサ)」
遠位尿細管と輸入・輸出細動脈の接合部を傍糸球体装置 〈JGA〉と呼ぶ。
傍糸球体装置JGAには以下の3つが含まれる。
- 傍糸球体細胞
- 糸球体外メサンギウム
- マクラデンサ(緻密斑)
JGAの中で遠位尿細管側にあるマクラデンサ(緻密斑)が低Cl刺激を感知し、(←試験にでます)
JGAの中で 輸入細動脈側にある傍糸球体細胞がレニンを分泌することで、 (←試験にでます)
血圧を調節している。
試験で
「レニンを分泌する細胞はどれか。図中から選べ。」
→JGAの中でも輸入細動脈側の細胞(つまり、傍糸球体細胞)を選ぶ。
という問題があったので、画像で確認しておこう。



JGAとだけ覚えていても、解けませんでした~(>_<)
問題文の細胞が、「JGAの中でどの細胞なのか」が分かったら楽勝!
①レニンを分泌する細胞はどれか?
→ 傍糸球体細胞
→ 輸入細動脈側の細胞を選ぶ。
②低Cl刺激を感知する細胞はどれか?
→ マクラデンサ(緻密斑)
→ 遠位尿細管側の細胞を選ぶ。
確認問題:医師国家試験【103B-14】解説
レニン分泌を促進するのはどれか。2つ選べ。
a コルチゾールの増加
b 輸入細動脈圧の上昇
c 交感神経β受容体遮断
d マクラデンサへの低クロール刺激
e レニン・アンジオテンシン系の阻害
答えは dとe
e の解説
レニン・アンジオテンシン系を阻害するとアルドステロンが低下し、血圧も低下するから
フィードバックでレニン分泌が亢進するね。


終わりに
お疲れ様でした。
参考になれば幸いです。
分からない事・疑問点・質問がありましたら、お問い合わせ or SNS(下記)にどうぞ。
誤字脱字・新しい情報・覚え方の提案も、共有させて頂けると幸いです。
「ゴロゴロ医学」では覚え方・ゴロ・まとめを紹介しています。
覚えることを最小限に抑え、コスパ良い勉強をサポートします。
不定期の更新になりますので、
【 公式X/twitter 】 または 【 公式Instagram 】 のフォローをお願いします 。